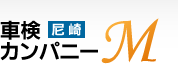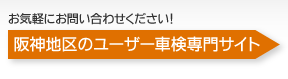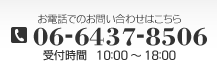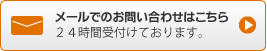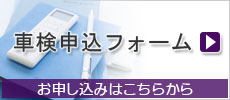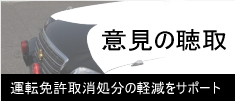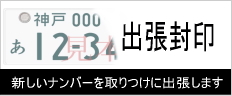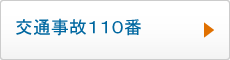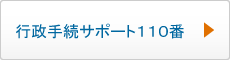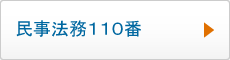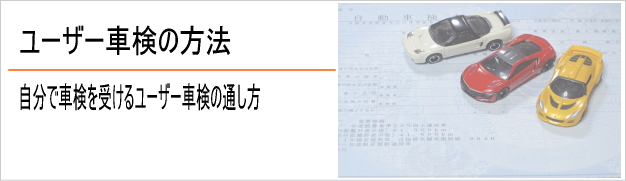

ユーザー車検に必要な書類の確認をしておきましょう。
自賠責保険は車検カンパニーMでも手続きができます。
車検が切れている場合は25ヶ月で手続きする必要がありますので注意してください。
| 事前に準備するもの | |
|---|---|
| 自動車検査証 | (車検証) |
| 自動車損害賠償責任保険証明書 | (新旧の両方) |
| 使用者の印鑑 | |
| 自動車納税証明書 | (継続検査用) |
| 陸運局の窓口で配布・購入できる | |
|---|---|
| 継続検査申請書 | |
| 自動車検査票 | |
| 自動車重量税納付書 | |
| 点検整備記録簿 | (後整備の場合は不要) |
自賠責保険の手続きを車検カンパニーMで行うと、
車検書類一式を無料で作成いたします。
ユーザー車検の最大のメリットは、費用を安くおさえることができることです。
整備費用や代行手数料がかからず、諸費用のみで車検を受けることができます。
※諸費用とは重量税、自賠責保険、印紙代など車検を受ける際に必要な費用です。
| 乗用車 | 貨物4ナンバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 重量 (1t以下) |
重量 (1.5t以下) |
重量 (2t以下) |
総重量 (2t以下) |
|
| 車種 | アルト ミラ など |
マーチ フィット など |
カローラ アベニール など |
クラウン セドリック など |
カローラバン ハイエースバン など |
| 自賠責保険 2021年4月1日より |
19,730円 | 20,010円 | 14,280円 | ||
| 重量税 ※ | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円~ |
| 印紙代 ( 3ナンバークラス ) |
1,800円 | 2,100円 | 2,100円 (2,200円) |
2,100円 (2,200円) |
2,100円 |
| 車検費用合計 | 28,130円 | 38,510円 | 46,710円 (46,810円) |
54,910円 (55,010円) |
22,980円~ |
車検前に最低限チェックする項目です。車の下回りは必ずチェックしましょう。
| 常点検として最低限チェックする項目 | |
|---|---|
| 灯火類 | ハイビーム等、シートベルト、サイドブレーキ |
| オイル | エンジン、ミッション、ブレーキ |
| タイヤの溝、はみ出しは無いか | ホイールキャップ等は受検前に必ず外してください |
| ワイパー | |
| ウインドウオッシャー | |
| ホーン | |
| マフラーの排気漏れ | |
| ブーツ等の破れ | |
| ブッシュのガタ等 | |
| 下回りは必ずチェックしましょう | |
| オイル漏れがひどい場合は修理が必要です。 オイルがにじんでいる程度ならば問題ないです。 足回り、下回りは洗車場などで洗浄してから検査に行ったほうが良いでしょう。 |
|
| ①受付へ | |
|---|---|
| 受付で予約の確認をした後に、ユーザー車検の手順などが書かれた用紙をもらいます。 そして、下記の用紙を購入します。 |
|
| 検査申請書 | 走行距離を記入 |
| 検査票と手数料印紙 | 3ナンバーは100円増、予約番号を記入 |
| 重量税印紙 | 車検時に必要な重量税を納付します |
| 定期点検記録簿 | 普通車と貨物では用紙が違います |
| ポイント | |
| ここでは、自賠責保険も購入(継続)することができますので手続を済ませておきます。 | |
| ②書類の記入 | |
|---|---|
| 買った書類(4枚)を記入します。 名義変更と同時にする場合等の書類についてはこちらでご確認ください。 |
| ③受付へ | |
|---|---|
| すべての用紙の記入が終わったら、「ユーザー車検受付」で用紙のチェックを受けます。 上記の用紙以外に、車検証・納税証明書・自賠責保険が必要です 記入ミスなどがあった場合は修正してチェックしてもらいます。 問題がなければ、ラインに通して点検を受けます。 |
| ④ラインに並ぶ | |
|---|---|
| 車種によって並ぶラインが違います ↓神戸の場合 |
|
| 1番と4番レーン | 小型4WD |
| 2番と3番レーン | 小型車 |
| 5番と6番レーン | 大型車(トラック等) |
| 初めての方は4WDレーンで受けることをおすすめします。 検査方式がマルチテスター方式なので一般の検査方法より簡単です。 |
|
| ポイント | |
| 初めての方は検査員に『初めてなのでお願いします』と一声かけておけば、 検査ラインに入っても検査員が気にかけてくれます。 | |
| 外観廻り及び電気廻りの検査 | |
|---|---|
| ① 灯火類の点検 | 車幅灯は白系統のもの(青などはダメ) ヘッドライトにフォグがある場合や字光式ナンバープレートは その部分もチェックされます。 |
| ② レンズ等の割れ | |
| ③ ヘッドレストの有無 | |
| ④ 封印の損傷の有無 | |
| ⑤ 発煙筒 | 意外と忘れがちです |
| ⑥ ホーンの音等 | |
| ⑦ ワイパーの動き具合、ウォッシャー液の噴出 | |
| ⑧ タイヤの溝、はみ出し | ハブボルトチェックのため、ホイールキャップは外しておきましょう。 |
| ⑨ 窓のフロント部のフイルム | |
| ⑩ 貨物車は仕切り棒の有無 | 左後スライドドアのチェックがあります。 |
| ⑪ 黒鉛チェック | ディーゼル車はここで黒鉛チェックを行います。 |
| ⑫ 車台番号とエンジン形式等のチェック | |
| ポイント | |
| ボンネットを開ける必要がありますが、ワンボックスカーは助手席のシートを開ける必要がありますので、前もって注意が必要です。 | |
| 電球切れはその個所を軽く叩いてみましょう。光る場合があります。 | |
| 発煙筒など借りれるものは周りの人に借りる手もあります。(もちろんですが、検査員はいい顔をしません) | |
| サイドスリップの検査 | |
|---|---|
| ① ランプが青色になったことを確認してから進入します。 | FF車(前輪駆動)は進入前にFF車申告ボタンをを推してから入ります。 |
| ② ハンドルをまっすぐにして、ゆっくり前進します。 | トーに異常があるとチェックが入ります。 -5.5㎜から+5.5㎜までなら合格です。 |
| ポイント | |
| 外車は特例がある場合があります。 | |
| 不合格の場合でも、最後の検査終了の受付で確認をしましょう。(合格になる場合があります) | |
| ブレーキ、サイドブレーキの制動力・メーターの誤差等の検査 | |
|---|---|
| FF車(前輪駆動) | 前ブレーキ スピード検査 後ろブレーキ サイドブレーキ の順序で行います スピードメータは40キロで申告ボタンを押します |
| FR車(後輪駆動) | 前ブレーキ 後ブレーキ サイドブレーキ スピード検査 の順序で行います |
| マルチテスター(4WD用) | スピード検査 前後のブレーキ(同時)の順序で行います |
| ポイント | |
| スピード検査で落ちる方は、一気に上げすぎて測定器が追いついていない場合がほとんどです。 メーターを40キロまでゆっくりあげて2秒程静止させてください。 | |
| ブレーキ検査で落ちる方は、踏み方が甘いのがほとんどです(特に雨天の場合)。 ゆっくり踏み出しながらブレーキが作動しだしたら、おもっきり踏み込みましょう。 |
|
| 万が一不合格になっても、違うレーンでもう一度検査を受けてみることをおすすめします。 | |
| ヘッドライト光軸の検査 | |
|---|---|
| ① 白線に沿ってまっすぐ自動車を停止させるようにしましょう。 | |
| ② ヘッドライトをハイライトにして光軸を検査します。 | |
| ③ 4頭式のヘッドライトはロービーム側を厚紙などで覆いましょう。 | |
| ポイント | |
| 万が一、光力の不足で落ちたなら、停止線ギリギリまで前進してエンジンを3,000回転ぐらいまでふかしてみましょう。 | |
| ヘッドランプがくもっている場合もあるので布などで拭くといいでしょう。 (ノンコンパウンド式のワックスを使用すると効果的です) |
|
| 4WDマルチテスターはブレーキ、サイドブレーキの制動力、メーター誤差等の検査と ヘッドライト光軸の検査を同時にします。 |
| 下廻りの検査 | ||
|---|---|---|
| ① マフラーの腐食(排気漏れ)、触媒の有無 | ||
| ② ドライブシャフトの破れ | ||
| ③ ラックブーツの破れ | ||
| ④ その他ブッシュ関係のガタ | ||
| ⑤ ハンドルのガタ(特に外車、大型車) | ||
| ⑥ 地上高(車高9m) | ||
| ⑦ 燃料漏れ | ||
| ⑧ オイル漏れ(大) | ||
| ポイント | ||
| ここで不合格になると再検査となる場合が多いので、受検される前によく点検しておきましょう。 | ||
| 排ガス検査 | ||
|---|---|---|
| ① 自動車から降りてマフラーに検査棒を突っ込んでチェックします。 | ||
| ② ディーゼル車は排ガス検査は不要です。 | ||
| ポイント | ||
| エアコンは排ガスの量を増やすので5分ほど前からOFFにしておきましょう。 | ||
| 検査受け全体に対してのポイント | |
|---|---|
| 一度落ちても再度違うレーンで受検すると、まれに合格する場合があります。 気落ちしないでもう一度受けてみましょう。 ただし、検査レーンは一日2回までという制限があります。 |
|
| 電球の球切れ、ホイールキャップの外し忘れなど、目視で確認できる項目は他の受検者の邪魔にならないよう注意しながら
出口までバックで行き、検査終了の窓口の検査員に確認してもらう方法があります。 これなら、再度ならばなくても合格印がもらえます。 |
|
| もし、異常があった場合は整備し直して再度チェックを受けます(当日なら2回までOK)。 近くにテスター屋があるので、調整してもらうと良いでしょう。 |
| 車検に通らなかった場合 | |
|---|---|
| ① 限定自動車検査証を発行してもらいます。 | |
| ② 有効期限は最大15日あるので、それまでに必要な箇所を調整して検査を受けることができます。 再検査する場合は、手数料(1,300円)が発生します。 |
|
| ③ 再検査する場合の予約は不要です(神戸・南港)。 | |
| ④ 当日に車検が切れている場合は、仮ナンバーを発行して陸運局まで走行します。 |
GTカーなど、走り屋と呼ばれる方はいろんなパーツを取り付けているので、心配なると思います。
そこで、実際に車検に通るパーツと通らないパーツを表にしました。
| 車検に通るパーツ | |
|---|---|
| 自作ブローバイキャッチタンク | 戻してあれば問題ありませんが、大気開放はNGです。 |
| むき出しのエアクリ | 取り付けがしっかりしていれば問題ありません。 |
| 触媒の遮熱板 | 無くても通りました。 |
| ピロテンションロッド | 赤色でも問題ありません。 |
| 車高調 | バネのあそびが無ければ問題ありません。 |
| 大口径マフラー | 特にチェックを受けませんでした。 |
| フロントガラス上部のフィルム | 上部から20%までは問題がないようです。 |
| ダッシュボード上のツィーター | 取り付け具合はチェックされませんでした。 |
| フルバケットシート | 背面がむき出しでなければOKです。 |
| 追加メーター | チェックは受けませんでしたが、取り付けが固定されていないとチェックを受けると思います。 |
| 車検に通らないパーツ | |
|---|---|
| フルバケットシートの背面がむき出しのもの | 2名乗車に変更している場合は対象外。 |
| はみ出しタイヤ | |
| 触媒ストレート | |
| 青や緑などの色をしたヘッドライトバルブ等 | 外観ではなく実際に壁等に照らされる色で判断します。 |
| ブローバイの大気開放 | |
| 非可等式エアロミラー | |
| 規定よりも大きなGTウイング | 片側160mm、両方で320mm以内に収まり、形状が鋭くないものは可。 ※GTウイングに関しては各陸運局により差がありますので、確認が必要です。 |
ユーザー車検の予約の予約は事前に行いましょう。
予約はインターネットで予約ができます。
自動車検査インターネット予約システム
軽自動車検査予約システム
| 納税証明書紛失の場合 | |
|---|---|
| 神戸陸運局 | 陸運局の敷地内(整備振興会)で取得できます。 未納があった場合は、最寄りの県税事務所で自動車税を納付し、車検用の証明書を交付してもらいます。 |
| なにわ検査場 | なにわ検査場は、その場で納付することで納税証明書の交付は受けることができます。 |
| 軽自動車 | 納税証明書を紛失した場合は、車検証に登録されている市区町村で再発行する必要があります。 |